


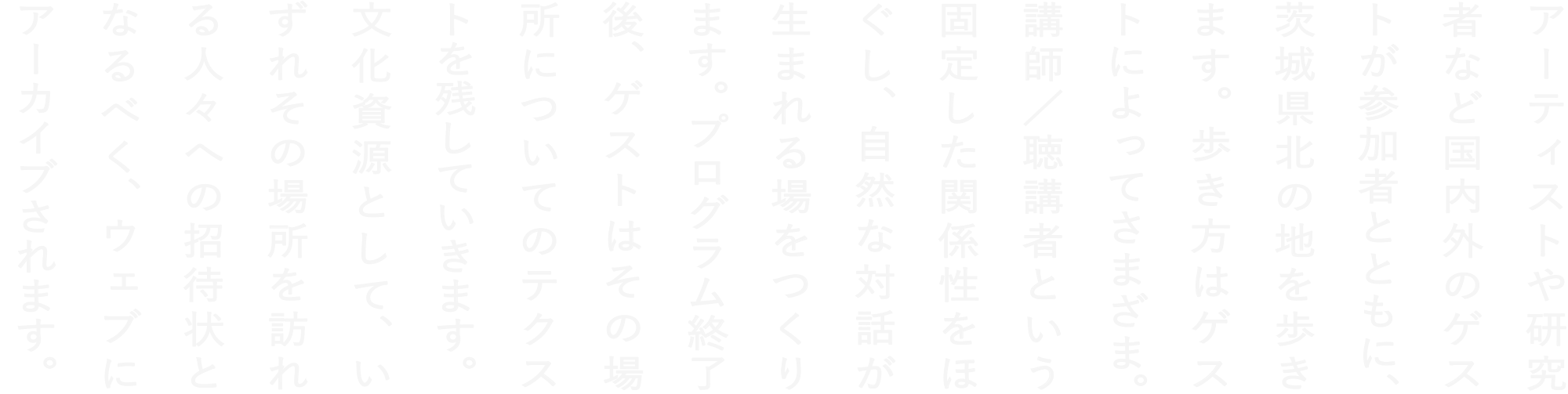

第3期(2021年2月)の募集を開始しました
小学校の学区内に国道123号と118号が通るあたりに僕の実家はある。ちょっと家族で出かける時なんかは、どちらかの道をよく北に向かって車を走らせていたように思う。常北町から御前山なんかを通って栃木県に抜ける123号と、大宮町から大子を経由して福島県に入る118号。太田方面に向かう349号も馴染みがあり、6号国道は勝田まではよく行っていたけど、日立、北茨城方面は少し縁遠かった印象がある。県南はもとより、石岡や土浦といった水戸より南側に行く機会は少なかったと思う。なんとなくの自分にとっての茨城の原風景というと県北の内陸寄りのあたりのことを思い浮かべるのは、かつての両親に連れられての行動範囲に由来するものだろう。
先月、常陸太田駅から程近い、木崎二町というあたりを歩いた。四十年も前の話だが、父親が佐竹高校(*)の教員をしていたこともあり、三歳くらいまでそこに住んでいたのだ。当時住んでいた住所と、古い数枚の写真を頼りにそこまで歩いてみた。家の場所はすっきりとした空き地になっていたんだけど、写真に映り込んでいた界隈の建物なんかをいくつか見つけてはちょっと興奮したりしつつ、天気も良くてなんだかいい時間だった。
ぼんやりとした記憶があるような気がしていたのだけど、歩き終わって戻ってきたら、一緒に歩いた友人が「中﨑くんは結局なんにも覚えてなかったんだね」ってポロっと言っていて、ほんとだ、何も思い出さなかったし全然懐かしくもなかったって気がついて、なんかおかしかった。小さい頃からアルバムを見返す習慣があったからか、かつて太田に住んでいたという認識はずっとあったけど、実際の記憶というよりはアルバムの写真越しに刷り込まれた記憶なのかもしれないなあとぼんやり今でも考えている。
実家のある水戸に帰ってきてしばらく経つが、各地での滞在制作も多く、地元には一年の半分もいないのが恒例になっている。仕事ではそれぞれの場所で積極的に地域に住む人たちと関わりながら作品を制作しているけど、一方で普段地元にいるときは、近所付き合いなんかはだいぶ消極的に過ごしている。もともと住んでいたのが郊外だったりもするのであまり地元に愛着ない気がしていたけど、震災の時期なんかはなかなかにこの場所に執着する自分がいて結構意外だった。それと、数年前の県北での芸術祭(*)に参加した頃から少しずつ地縁のようなものを改めて感じる機会が増えた気がしている。高校や予備校くらいまでの友人知人に改めて再会したり、親戚なんかが意外なところで繋がっていたり。地縁というか血縁というか、この場所に育ってどうにも切り離せない縁のようなものを薄々感じつつ、見て見ぬ振りのような過ごし方をしていたりする。
記憶がすっかり抜け落ちていて、かつ住んでた場所もすっぽり空き地になってしまった場所に立ってみたということと、四十年くらい前の写真に自分と一緒に映り込んだ建物が、自分の目の前に今も建っているということの対比が、どちらも冗談みたいなんだけどなんだか妙にリアリティがあって、このところ気になり始めている自分にまつわる縁のようなものについて少し輪郭を与えてくれているような感じがしている。忘れていたり無自覚なものから形作られる姿みたいなこと、ぼんやりと消えていく記憶と切れかけながらも微かに残る縁のちぐはぐな関係みたいなものにちょっと関心を向けてみようと思う。
*1 佐竹高校 旧茨城県立佐竹高校。現在は閉校。
*2 KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭
*県内の地名は当時の記憶にある合併前の地名を使用している。
中﨑 透 美術家
1976年茨城生まれ。美術家。茨城県水戸市を拠点に活動。看板をモチーフとした作品をはじめ、パフォーマンス、映像、インスタレーションなど、形式を特定せず制作を展開している。展覧会多数。2006 年末より「Nadegata Instant Party」を結成。2007 年末より「遊戯室(中﨑透+遠藤水城)」を設立。2011年よりプロジェクト FUKUSHIMA!に参加、主に美術部門のディレクションを担当。
漠然と、遠くに行きたいと思うことはあるけれど、実際には動けないまま時が過ぎて、そんなことを言っているうちに気づけば家族もいい年になって、余計に動けなかったりで、もう長いことぐずぐずしている。私にはずっと、知らない街でやり直したいという気持ちがあった。そんな私からすると、二十代の若さでふるさとを遠く離れ、突如、常陸太田に現れた「日坂さん」の存在は眩しかった。
私たちは共通の友人を介して知り合った。聞けば「干し芋が好き」という理由で茨城に来て、常陸太田に住んで服を作っているとのことだった。面白い子が来たなと思っていたのも束の間、いつのまにか良き話し相手となり、気がつけば昔からの友人のように親しくなっていた。
私の母も服を作るのが趣味だった。ガラス張りで日当りのよい部屋が母の裁縫部屋だった。部屋の奥に置かれた大きな足踏みミシンと、細長いテーブルに横並びに置かれた二台のミシン、その横に置かれたトルソー、筒状の布、それらがたくさん立てかけられて少しずつ崩れ落ちていく黄土色の砂壁、スチームアイロンの甘い匂い、ラジオから流れる音楽と時々かかるミシンの音。小さな私は、そこで作業をする母を見るのが好きだった。
母を亡くして二十年の時が過ぎた今でも、その部屋は時が止まったままそこにあった。埃をかぶりながらあり続けるそれらノスタルジーの産物を、いい加減なんとかしなくてはいけなかった。そのきっかけを探していた。
「いろんな人の記憶を、一着の服にしたらどうか。」と言い出したのは私だった。日坂さんはそれに賛同してくれた。とにかく私は服を作りたかったのだ。
以前一度だけ、日坂さんが城里にある私の実家に遊びにきてくれたことがあった。一通り部屋を案内した後、父と一緒になって、納戸にしまってあった織り機や、おもちゃの刺繍ミシン、裁縫道具などを引っ張り出して、日坂さんに使って欲しいと言って持ち帰ってもらったのだった。あんな埃まみれのミシン、今思えばどう考えても迷惑だったと思うのだが、日坂さんは「いいんですか?」と言って持ち帰った。
こうして実家のミシンが太田に移動したのだった。
日坂さんが居るのは鯨ヶ丘という高台の土地に佇む旧料亭で、太田の街を一望できる眺めの良い場所だった。そこからはたくさんの家の屋根が見えて、その中に流れる時間を想像するには最高のロケーションだった。私は一番眺めの良い場所に立ってみては、そこからのぞく無数の家庭の気配に圧倒された。
私はこれまで、常陸太田を含む県北地域にはあまり馴染みがなく過ごしてきた。それが日坂さんがやって来たことで、実家のミシンが移動して、私も吸い込まれるように太田に来てしまったのだから、もう馴染みがないとは言えないかもしれない。遠くから突然やって来た人との出会いがきっかけで、実家で埃をかぶっていたミシンが太田で動き出すというのも、なかなかおかしな話だけれど、ハプニングとかエラーみたいな、思いがけない出来事が起こる時ほど、今まで見えていなかったものが見えたりすることを、私は知っている。
さて、これからどのような服を作ろうか?
ノスタルジーの産物を未来へ送り出すための準備をはじめよう。
仲田 絵美(なかた えみ)
1988年茨城県生まれ。写真家。自身や家族などを撮影した作品「美しい速度で」により、2012年第7回写真「1_WALL」グランプリを受賞。翌年2013年、グランプリ受賞者個展として「よすが」(ガーディアン・ガーデン)を開催。2015年、写真集「よすが」(赤々舎) を出版し、第41回木村伊兵衛賞ノミネート。近年の展覧会に「yosuga」「home」(QWERTY VISION ♯4)、「なんでもない」(krautraum)、「あわい」(OGU MAG)などがある。現在は服飾作家の日坂奈央とともにノスタルジックシンドロームユニット【nimono】を結成し、今後の活動に向け準備中。
ウェブサイト http://nakataemi.com/
こんにちは。懐かしむことに執着しがちなユニットnimonoの日坂奈央です。今日は、晴天に恵まれた二〇二一年二月十四日に行われたワークショップ「服と巡る」について日坂奈央さんにいくつか質問していこうと思います。よろしくお願いします。
Q.日坂奈央
A.日坂奈央
Q.ワークショップはどこで行われたのですか?
A.茨城県常陸太田市の鯨ヶ丘商店街にひっそりと佇む、私の活動拠点である「メゾン・ケンポク」です。昔から、「大根坂」と呼ばれている、かなり急な坂の横に建っています。そんな場所から、nimonoと参加者をオンラインで繋いで行いました。
Q.気になる場所ですね。タイトルは「服と巡る」ですが、服と巡ったのですか?
A.はい、服と巡りました。参加者に服の写真とエピソードなどを用意してもらい、話してもらいました。その後に、その服にまつわるエピソードや感情を元に、形や色、模様や素材などの、服に関するキーワードに置き換えると何か? と言う少し難しめな課題を与えました。困っている方もいました。すごく簡単に説明すると、そんな感じです。
みなさん、けっこううまいこと服と巡れていました。自分の服だけでなく、他の参加者の話を聞くときは、その人の服と巡ることができていたと思います。絵美さんの話の引き出し方が巧みで、参加者の思いがけない記憶が蘇ったりしていました。その時は、あ、服と巡っている! と強く感じました。
Q.「服と巡る」って、どういうことなのでしょうか?
A.私は、過去の記憶が大好きで、記憶と服がセットみたいになっていることがよくあります。あの日はあの服を着て、あんなことをした。とか、あんなことをした日はあの服を着ていた。という懐かしみ方をします。これは私的にスタンダードな「服と巡る」です。でも正解はないので、自由に服と巡って、あ〜服と巡ったなあと思ったらいいのだと思います。
Q.どんな時に服と巡りたくなるのですか?
A.私は兵庫の実家にいる時から、服と巡ったり懐かしむ癖があった気がします。その癖が、常陸太田に引っ越して初めての一人暮らしを始めてから今も、爆発しています。おそらく寂しさや過去への執着なのだろうなと感じています。そろそろ懐かしんでる場合じゃないとも思いますが、懐かしいという感情のことがとても好きなので、やめられなさそうです。
Q.今、服と巡って思い出すことは実家にいる時のことですか?
A.はい、基本的には。もうここに住みだしてから二年半が経つので、ここでの事を思い出すこともあります。でも、それによって求めている感情が生まれることはまだ少ないです。
Q.もっと先になれば服と巡って常陸太田を思い出し、求めている感情が生まれそうですか?
A.なんとなくそんな気がしています。今の私の常陸太田での生活を、例えばここを去った私の過去だと思って見てみると、すごく変で貴重なありがたい日々だと思えます。あの服を着ていた時に、ホームシックで泣いたな、とか、仲の良いおばちゃんと遊んだな、とか、おしゃれする気力もなくあの服ばかり着て暗くてじめっとした部屋で制作したな、とか、メゾンの台所でみんなとワイワイしたな、とか、良い記憶も辛い記憶も、過去となれば愛しいものになる気がします。と言うことは、今を過去だと思って過ごせば良いのかも、とも考えましたが、それはなんか違いました。
いつまで私が常陸太田にいるかも、もしかしたらずっといるかもわからないけど、ここでの生活を服と巡って思い出す日がくるのは楽しみのひとつです。
日坂奈央(ひさか なお)
1995年生まれ。神戸芸術工科大学ファッションデザイン学科卒業。2018年より茨城県北地域おこし協力隊としてメゾン・ケンポクを拠点に活動。主に服を作ったりしている。「夢ちどり」というフリーペーパーや、「紅はるか」という本を制作。最近は作品の販売にも挑戦している。
まだ大学生だった一九九三年に、現在私が勤務する日立市郷土博物館で初めて写真家ユージン・スミスの作品に触れました。もちろん日立を撮っていたことにたいへん驚きましたけれども、なによりスミスの眼差しといいましょうか、彼が世界中のさまざまな状況に生きる人々へ向けた愛と畏敬の念のようなものに感じ入ったことが、その後に私がスミスを調べはじめるきっかけとなったと思います。そして一九九六年に東京都写真美術館で開かれた展覧会「ユージン・スミスが見た日本─沖縄・日立・水俣─」を観に行ったことによって、いつか必ず日立の写真で展覧会を企画したいと決意したのです。
その後、様々な方のご協力を得て日立撮影について調査させていただき、一応の成果として二〇一〇年に展覧会を開催することができました。さらに追加調査を行なって文章も書いてはみたものの、日立の事柄にのみとらわれすぎて近視眼的になったり、またデータの面白さにハマってしまったりして看過していたことがなんと多いことか。二月二十二日にみなさんのご意見に触発され、気付いたことが多々ありました。どうもありがとうございました。
スライドの最後に、一九七一年にスミス夫妻が水俣の街を見渡す写真を映しました。その風景はどことなく日立の谷あいの工場群を彷彿とさせます。ちょうどその一〇年前、一九六一年のスミス来訪時には高度成長のただ中にあった日立ですが、二〇世紀初頭には煙害という大きな問題が起きています。一方戦後の水俣では、工業化が豊かな自然と人々をスポイルしていました。それぞれに全く異なる歴史を持つ土地どうしではあるものの、スミスの作品と活動を見ていると、「漁村」「工業」などのいくつかのキーワードとともに日立と水俣という二つの街が相似形をなすように思われるのです。
スミスがどこかの時点でこのようなことを意識していたかどうかは定かではありませんけれども(どうやら少しはあったようですね)、日本において後期の充実した創作を行なったスミスは、自らの身体に砲弾の破片をのめりこませた日本および日本人への興味を越えた愛着と、偶然にも長く関わってしまったゆえの友情のようなものが輻輳した感情を抱いていたのではないかと私は推察しています。いみじくも異邦人ユージン・スミスが、日本という〈地域〉を映し出す鏡のような存在になったのだなあ、などと、ぼんやり考えています。
日立には、大きく変わってしまったところと、あまり変わっていないところとがあります。どこの土地にも言えることでしょうし、至極当然のことのように思われますが、日立に暮らしているとかなりの割合で〈変わっていない〉に出くわすことが多いです。ユージン・スミスについてのあれこれをあらためて考え、みなさんとお話しできたことで、その思いを新たにした次第です。
大森 潤也 日立市郷土博物館学芸員
1970年、茨城県日立市生まれ。1996年から日立市郷土博物館の美術担当学芸員。主な研究分野は近現代絵画および日立・茨城の美術。主な担当展覧会は「画家たちの巴里」(1998)「近代花鳥画考」(2000)「加守田章二と竹内彰」(2006)「ユージン・スミス─東洋の巨人・日立をとらえた眼」(2010)「増田聡子展」(2015)など。大学時代にユージン・スミスの日立撮影を知って以降、その関連写真・資料を調査している。
知らない土地で作品をつくる機会がある。
現地で出会い、ことばを交わした人の話に耳をすますことから、すべてがはじまる。
中舟生駅から国道沿いを少し行くと、〈紙のさと〉があった。工房は、菊池ちあきさん、大輔さん姉弟とご家族で営まれている。
広い店内に向かって「こんにちは」と声をかける。同世代であろう女性が出てこられた。「澤さん、怪我されたんですよね」とお互い苦笑いする。
訪ねる日の前夜、今回の催しを企画したキュレーターの澤さんから骨折したと連絡が入り、思いがけず一人で行くことになったのだ。
「ところで、何やるんでしたっけ」。彼女のさっぱりした物言いに、どこか安らぐような気がした。
紙漉きの技術は、中国で発明され、朝鮮を通じて日本に伝えられた。
紙の原料となる楮は本来南方系の植物だ。そのためか昼夜の寒暖差が大きく、水はけもよい工房周辺の土地で育つ楮の繊維は短く細くしか成長しない。だがその楮を使った西ノ内紙は、強靭でしなやかな仕上がりになる。
江戸時代、西ノ内紙は水戸藩奨励の専売品として江戸の町に運ばれ、濡れても字が滲まず、虫害にも強い丈夫な紙として、提灯や傘、大福帳と様々なものに用いられた。
西ノ内紙の話をしてくれたちあきさんは、日本の紙漉きは地域や用途など、それぞれの求めに応じて楮という同じ原料であっても全く違ったかたちに仕上げてきた歴史についても教えてくれた。そして静かな声で言われた。
「人にも土地にも負担をかけず、あるものを最大限利用していくと、必要なものが残るんです」
ワークショップでは、工房で随時体験ができるすき絵――漉いて乾かす前の紙の上に、染めた楮の繊維を乗せ、絵を描く技法――で字を書くことを提案した。
「それだと字に触れられますね」。ちあきさんのことばに紙漉きに携わる人の思いを感じた。
〈触る〉ための字には、「藝」の字を選んだ。
「藝」の字の成り立ちは、人が若木を植える姿を象り、木を植え、奉りながら育む様子だ。
漢字が生まれた古代中国では、書き順という意識はまだない。
「藝」の字の古い書体を実際に書こうとすると、若木の苗は既に植えられたのか、まさにいま植えようとしているのか、まず人がいて若木があるのか、若木があって、そこに人が寄り添っているのか、書き順によって情景が変わることに気づかされる。
終盤、参加者の方から、「紙について知識を持たれているなら、西ノ内紙が他の地域の楮紙と違うところをもっと捉えてください」と声が上がった。
西ノ内紙のことも、かつて西野内と呼ばれたこの土地のことも、菊池さん姉弟のことも私はまだなにも知らない。時間の過ごし方を間違えたことに気づいた。
帰り際、菊池さん姉弟に、書を書きやすい紙を教えてくださいと、いまさらお願いした。ふたりは薄手の大判の紙を三種類選んでくださった。
以前買い求めた西ノ内紙は、定番の厚いもの――普段、私が使わない紙だった。そのとき私は、西ノ内紙そのものを知ることにばかりに囚われ、字を書くときにどんな紙を使いたいかという、私と紙との関わりについて失念していた。
ちあきさんの言葉がいまも耳に残る。
「紙は、私たちがどれだけいいものといっても、書き手との相性は別物。まずは試してみてください」。そう言って、彼女はにこりとされた。
彼女の言葉に、どんなかたちで応じられるのか。
紙を抱え、思いをめぐらせながら、東京へ向かう電車に揺られていた。
華雪 書家
1975年京都府生まれ。書家。立命館大学文学部哲学科心理学専攻修了。92年より個展を中心に活動。文字の成り立ちを綿密にリサーチし、現代の事象との交錯を漢字一文字として表現する作品づくりに取り組むほか、〈文字を使った表現の可能性を探る〉ことを主題に、国内外でワークショップを開催する。刊行物に『ATO跡』(between the books)、『書の棲処』(赤々舎)など。作家活動の他に、『コレクション 戦争×文学』(集英社)、『石原慎太郎の文学』(文藝春秋)をはじめ書籍の題字なども多く手掛ける。
作品収蔵先:高橋コレクション(東京)、ヴァンジ彫刻庭園美術館(静岡)、うつわ菜の花(神奈川)など。
ええ、私の優しい父にべらぼうな額の借金があることがわかりまして、思わず家を出てしまいました。電車に乗って、でたらめに何度も乗り換えました。部活帰りらしき高校生たちに紛れて、一両だけの電車に乗りました。夕暮れ時にたどり着いたのは、夢にだって現れたことがない、私の育った街とはひとつも似たところがないような街でした。目の前には丘を巻く曲がりくねった道がありました。子どもたちは、夕焼けに向かって小走りに登っていくわけですが、腰の曲がったおじいさんは「おい! 丘陵、削ってんじゃねー」と呪いにも似た言葉を並べながら息を切らせて登っていました。
私もつられて丘の上まで行くと、海の上にプカプカと浮かんだお椀のような形の街がありました。丘のてっぺんで古い土蔵や町屋が身を寄せ合い、時計屋さんとうどん屋さんと駄菓子屋さんがあり、子どもが自転車に一人で乗っていました。
ぽつりと灯る明かりに「月の井旅館」の文字が浮かび上がっています。
「私、しばらくこの街に暮らしてもいいでしょうか」
女将のような黒髪の女に尋ねると、「まずは出前を取りましょう」とうどん屋に電話をかけ、レコードをかけてくれました。ナット・キング・コールでした。
鯨ヶ丘。
それが、この街の名前だそうです。しかし、旅館の窓からは海の断片も見えません。
「いつか窓からクジラの形の雲が見えるかもしれませんよ、ふふふ」
大きな黒い目をした女が笑いました。
私はその街に暮らしました。大きな窓がある広い部屋で、遠くまでよく見えました。
一月五日。女の子が雪でかまくらを作っていました。おもちゃのラケットをスコップがわりにして、いじらしく雪を集めていました。クジラの形の雲はまだ見えませんでした。
三月二十一日。三月も終わりだというのに、お雛様のお祝いが町のあちこちで行われているようです。とんかつ屋さんにも立派な雛飾りがありました。私の育った街では、早くお雛様をしまわないとお嫁には行けなくなるとひどく脅されたものですが、あれは何だったのでしょうか。
四月三十日。道端にランドセルを背負った男の子が座り込んで、泣きじゃくっていました。
「今日妹か弟が生まれるのに、迷子になっちゃったよー。お父さんに怒られちゃうよ」
そう言うと、その子は一目散に坂を下りて行きました。彼は無事に妹か弟と会えたのでしょうか?
七月十九日。暑い日でした。女子高生三人が通り過ぎていきました。 「山セン、ちょームカつくよ。授業眠いし」 「ねーねー、あれ食べよーよ! 氷! 氷!」 「えーお金ないよ」 空に浮かぶのは入道雲でした。
八月十六日。ふと家に帰りたくなりました。いつも坂の上から下の世界を眺めていると、下の世界には得体の知れない楽しさを孕んでいるように見えるのです。坂を下りて駅に着き、切符を買おうとすると、中年でも若くもない女が向こうからやってきました。 「十年ぶりにこの街に帰ってきたのに、誰も迎えに来てくれなかった」と泣いています。私は改札をくぐる勇気を喪失しました。
九月二十五日。写真館の奥さんが突如として失踪したらしいのです。蔦が絡む素敵な写真館で、この街の子はみんなそこで七五三の写真を撮るのだそうです。奥さんは女スパイだったのよ、と黒髪の女将がこっそり教えてくれました。奥さんは、六十八歳だったそうです。
十一月二日。たくあんに夢中の男の人が庭先にぎっしりと大根を干していました。夕方その大根の一部が盗まれてしまい、男は足を引きずりながら犯人を追いかけました。 「待て、大根泥棒!」 という声が町に響きました。
十二月八日。雪の日です。しーんとしていました。雪の中、田中耕三さんの家の洗濯物がいつまでも干しっぱなしでした。どうしたのでしょう。
十二月三十日。駅に向かいます。さようなら、鯨ヶ丘。ついぞクジラの形の雲は見えませんでしたが、私は帰ります。
この街では、いくら待っても娘からの手紙は届かず、しばしば誰かが家出し、赤ちゃんが泣き、頼りになる塗装店もあっさり閉店するわけですが、私はその街を愛しました。思えば、まだ一枚の写真も撮っていませんでした。 ああ、よくカメラを持ってうろうろしていたあのおじさんは、どうしたのでしょうね? あの帽子をかぶった無口なおじさんですよ。商店街から駅に向かう道でよく見かけたのですが。 「さあ。でも後に残った写真には、一つも色がついていなかったのよ」 女将がまたナット・キング・コールをかけてくれました。
アンフォケッタボー♪
そうですか、色のない鯨ヶ丘も見てみたかった。 うどん、好き、うざい、わーん! 赤ちゃん、氷、スパイ、泥棒! そんな無数のものでできあがった愛しき一年間でした。 今から電車に乗ります。
追記) 二〇一九年三月二十一日にメゾン・ケンポクで「記憶の中を歩く」というワークショップが行われました。参加者は、ある男性が約四十年前に撮りためたモノクロ写真を見ながら、そこに潜む物語を自由に「妄想」しました。この文章は、二十三人分(私自身を含む)の妄想を掛け合わせた完全なるフィクションです。ただし、鯨ヶ丘は現存する町で、写真に移された光景はかつて確かに存在したものです。大勢の妄想をミキサーに入れてガーっとブレンドしてみれば、本当にその町で起こったかもしれない何かができあがった気もしますし、全く別物になってしまったかもしれません。今となっては、全ては誰かの記憶の中に――。
川内 有緒 ノンフィクション作家
1972年東京生まれ。米国の企業やシンクタンク、フランスの国連機関などに勤務し、国際協力分野で12年間働く。2010年からはフリーライターとして評伝、旅行記、エッセイなどを執筆。自分らしく生きること、誕生と死、アートや音楽などの「人生の表現活動」が主なテーマ。著作は『パリでメシを食う。』(幻冬舎)ほか。「バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌」(幻冬舎)で新田次郎文学賞、「空をゆく巨人」で第16回開高健ノンフィクション賞を受賞。現在は子育てをしながら、執筆や旅を続けている。
私はカンブリア紀の山の中、日立鉱山の本山社宅生まれです。終戦の年の戦中生まれですから、戦争のことは親から聞いているのみです。社宅といいますが、四〜六軒入った長屋で、こんな長屋が本山の谷底や急傾斜地、山の尾根などに所狭しと並んでいました。日立市街は終戦間際の爆撃や艦砲射撃で壊滅状態でしたが、日立鉱山には全く爆撃は行われませんでした。ただ、時々グラマン戦闘機が谷筋に沿って低空飛行しながら機銃掃射したそうです。そのため、母は私を抱いて防空用のトンネルに逃げたり、家で布団をかぶっていたそうです。実は私にはもう一つ危機がありました。母のお腹の中にいた時、不動滝で土砂崩れがあり、同じ長屋の二軒を含め六軒ほどが埋まったり流されたりし、四名が亡くなっています。
小学生の頃は一万五千人ほどが本山で暮らしており、本山小学校には二千人近い生徒がいました。日立市街より物資も豊富で文化に接する機会も多く、活気溢れる社会でした。道路とバス交通の整備はまだなので、子供達は本山から御岩山経由で玉簾まで徒歩で遊びに行き、里川で遊んで帰ってくるのが普通でした。春には金山までカジカ魚捕りに出かけます。金山は現在カンブリア紀の化石を探索している所です。本山から紅葉橋まで歩き、そこから尾根を一つ登って数沢川の上流部へ下ります。昔ここの綺麗な沢にはカジカがたくさんいました。夏休みになると歩いて大雄院まで行き、さらに鉱山電車で助川まで乗って、海水浴します。それもほぼ毎日です。帰り道の登りは辛かったですが、心身の鍛錬になりました。小学生も高学年になると野球はしたいのですが、本山には校庭以外には広場がないので、なかなかできません。鉄棒や砂場での床運動を遊びの中でやりました。蹴上がり、大車輪、空中前方回転、バック転などができました。
中学は町の助川中学校に通いました。この頃にはアスファルト舗装され、バスは頻繁に運行されており、朝七時過ぎの超満員のバスに乗って通います。この頃は鉄筋コンクリート作りのアパートが沢山建ちました。私はローラースケートに熱中し、一番バスが通る前の五時すぎに本山から大雄院経由で杉本まで滑り下ります。マイカーが普及する前なので、車は全くなく、道幅一杯にスラロームしながら滑るのは緊張と爽快の連続です。大雄院から先は鉱山電車と競争です。しばらくすると、鉱山から危ないからやめさせろとの指令が出て、できなくなりました。中学校の部活は吹奏楽部、楽器はトランペットです。
高校時代は水戸一高の吹奏楽部を創立して、毎日のように遊んでいましたが、進学が近くなるとストレスが溜まります。休みの日は下駄トレッキングでストレス解消が日課でした。素足に下駄履きで家から高鈴山を経て神峰山を越え、自宅へ戻るというコースです。ここを走って、自然の息吹、鳥のさえずりを感じると、ストレスは吹き飛んでしまいます。私にとって、カンブリア紀の山々はマザーフィールドなのです。
田切 美智雄 地質学者
1945年茨城県生まれ。茨城大学名誉教授。理学博士。東北大学大学院卒業。2008年、日立市の変成岩の一部が、日本最古の約5億600万年前のカンブリア紀の地層であることを発表。茨城大学退官後も日立市郷土博物館特別専門員として、多賀山地でのフィールドワークを行う。現在は日本最古の地層から、日本最古の生物の痕跡を探しだす研究を日々続けている。あらゆる世代へのワークショップや講演、またジオネット日立のインタープリター育成など、生涯教育の普及活動にも力を注いでいる。
数ヶ月前、路上でタコを見つけた。不意に出会うこととなった僕とタコ。結果としてタコ映画を作ることができた。そして完成後に千円札を拾った。これはご褒美だろうか。物語を作る類の人間の病気だろうか。僕はこんなことを繰り返している。今回は参加者と共にタコ的なものを求めて彷徨い歩くという素晴らしい機会を与えられた。
もし何も発見できなかったらという僕の不安を消し去る花壇に突き刺さったリカちゃん人形。人形と花の組み合わせが花壇をカルト的な祭壇にように変化させていた。参加者はまだ楽しみ方を知らないようだった。まあ誰も最初からビールを飲まないしタバコも吸わない。それをやるかどうかは、半分は自分の意志、もう半分は道に落ちているのに気付いてしまうかどうかに掛かっている。タコ的なものは嗜好品に似ている。食い方を知れば、それなりに美味い。片方だけの靴っていうのはビギナー級だが、塀の上に置いてあるというだけで少し面白い。僕たちより前にこの靴を発見した誰かが塀の上に置いたののではないかと推理した。靴を無くした人へ対する配慮だろう。だが第一発見者の気遣いも虚しく、我々は不思議な感覚に陥る。気遣いとは関係なく、逸脱していく意図。ここに旨味がある。意図が逸脱していくことに。さらに歩みを続けると、また靴を発見した。今度はショッピングカートに置いてある。この街にスーパーはない。参加者は首をひねる。確かにそうだ。何か理由があるが、その過程を知ることはできない。僕たちは結果だけ見ている。結果として植木にぶら下がることとなったカツラを眺めるしかない。被る以外の意図を与えられたカツラ。カラスや猫を追い払うためか。そんなことでは納得できない。参加者は全ては僕が仕組んだ事だと不審に思ったに違いない。しかし僕が置いたのはアフリカ的な武器だけだ。残念ながらそれは余りに不自然だった。僕は恥ずかしくなり参加者にもそれを暴露した。本物はもっと巧妙にバランスを保っている。そして、不意打ちのクライマックス。朽ち果てた◯◯の中で大量の◯◯◯とニュートン(科学雑誌)発見したところで、この町歩きが終わった。
一体何でこんなことをしているのか、甚だ自分でも疑問だと思いながら、小高い丘の上にあるメゾンケンポクから下界を見ていた。タコ的なもので世界は緩やかに構築されていくんだと思っている。逸脱した意図の成れの果てに立っている僕と鯨ヶ丘。リカちゃん人形やカツラがこの先も残っていくだろうか。しかし、この場所は見晴らしがいい。なんとなく、この場所が戦闘の拠点として優れているのではないかと考え始めた。見晴らしがいいから敵の様子を観察し易いし、入り口を限定することができる。それがこの地形の特性かもしれない。もし、仮に現代日本にテロリストが出現し、ここ鯨ヶ丘が彼らに占拠されたとしたらどうだろうか。太古の昔からこの地形が変わっていなかったとすれば、そうした事態が歴史上のどこかで起こったかもしれない。街への入り口を閉鎖し、空き家に籠城するテロリスト・イン・レジデンス。テロリストはアーティストと同じように場所を有効活用するだろう。もしくはそれ以上に。問題は、テロリストたちが出現したとして、彼らが一体どんな理念を持っているのかということ。それはまだ分からないがテロリストの映画を作りたいと思っている。それがこの街の特性を有効活用することなのではないか。もし仮にそんな映画が作れるとしたら、この街にタコ的なものとしてのテロリストをそっと置いてみたい。
鈴木 洋平 映画監督
1984年茨城県生まれ。多摩美術大学卒業。2014年、初の長編映画「丸」が海外の映画祭プログラマーや批評家の間で一躍注目を集めると、バンクーバー国際映画祭新人監督部門にノミネート、ウィーン国際映画祭、ロッテルダム国際映画祭に正式出品された。さらに名匠を輩出してきた映画祭「ニュー・ディレクターズ ニュー・フィルムズ」(2015)に選出されるなど、新人監督の作品としては異例の高評価を得ている。2018年短編映画「YEAH」がロッテルダム国際映画祭に招待出品される。現在は2本目の長編映画「ABOKKE」を制作中。
写真家ユージン・スミスが一九六〇年代に日立を撮影していたことを知ったのは、昨秋のこと。さらに調べると、日立市郷土博物館の学芸員、大森潤也さんが、二十年以上もその研究を続けていることが分かったのだった。
そして調べれば調べるほど、これほどの写真家が撮影した痕跡や成果が地元・日立にほとんど残ってないということも分かっていった。それはなぜか?
地域で生まれた重要な資料や作品が都市部へと流出し、地域には残りにくい、ということ。そして地域ではそういった資料や作品、情報がほとんど伝わらず、価値づけられにくい、ということ。これは実は博物学、そして美術における大きな問題なのだ。
大森さんの素晴らしい研究を地域に改めて紹介しながら、この問題を地域でシェアできないだろうか? それが今回の私の「茨城県北サーチ」だった。大森さんの研究は、私に新たな課題を示してくれたのだ。
そして華雪さんのプログラムにも同じことが言えるだろう。江戸時代から続く西の内紙を愛する人たちの熱意を、真摯に受けとめたアーティストによる、新たな展開がはじまるのかもしれない。
さてこの「茨城県北サーチ」を、福島県から二年続けて熱心に参加してくれている方から会の終わり際、こんな言葉をいただいた。
「このプログラムがすごくいいからこそ、こういう活動をゆっくりとやってほしい。」
こんな言葉こそが、私たち文化に関わる人間の糧だ。
今回のリサーチを通して私は、重要な文化を地域内外で等しく価値があるものとして捉え直すシステムを作りたい、と改めて思うようになった。慌てずに、でも決して消えることのない、持続可能な文化の発信とその仕組みを作っていきたい。
松本美枝子