

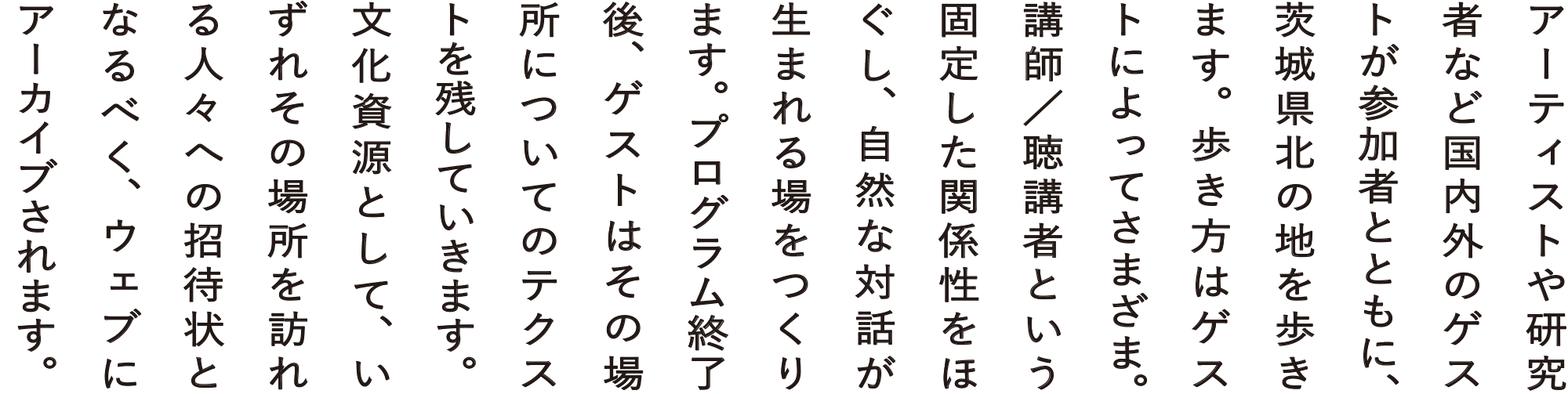

2020年もまた芸術祭ラッシュである。茨城県北地域は芸術祭とすこし異なるアプローチを昨年から始めた。作品ではなく作家や研究者(と)の体験を主眼とし、テクストとして10年後、100年後に受け継ぐことを目指す。今回は記録写真の一葉、手漉き和紙の一文字がいかに大きな時間の中に存在しつづけているかということを、手を使い足で歩きながら体験する。かつてあったもの、これから始めるトライを地域から掘り出し、掘り下げ、じわり日々の感情に結びつけられるか。我々自身の探究心にかかっている。
_ 澤隆志

2020年2月22日(土)
アメリカの著名な写真家ユージン・スミスが、1960年代に日立を撮影したことはあまり知られていません。その写真を長年、調査してきた学芸員の大森潤也と、貴重な資料を閲覧、実際の撮影場所を見学し、スミスの写真を地域資料として読み解いていきます。
終了しました
1970年、茨城県日立市生まれ。1996年から日立市郷土博物館の美術担当学芸員。主な研究分野は近現代絵画および日立・茨城の美術。主な担当展覧会は「画家たちの巴里」(1998)「近代花鳥画考」(2000)「加守田章二と竹内彰」(2006)「ユージン・スミス─東洋の巨人・日立をとらえた眼」(2010)「増田聡子展」(2015)など。大学時代にユージン・スミスの日立撮影を知って以降、その関連写真・資料を調査している。
撮影:松本美枝子

2020年2月23日(日)
国土が違えば木の径も異なり、紙漉きの大きさとして現れます。文字も誕生から今まで変化は止まらず、書家・華雪はその変化を創造の源とします。今回は「芸」一文字の誕生からイメージし、すき絵技法で字を書きます。
終了しました
1975年京都府生まれ。書家。立命館大学文学部哲学科心理学専攻修了。92年より個展を中心に活動。文字の成り立ちを綿密にリサーチし、現代の事象との交錯を漢字一文字として表現する作品づくりに取り組むほか、〈文字を使った表現の可能性を探る〉ことを主題に、国内外でワークショップを開催する。刊行物に『ATO跡』(between the books)、『書の棲処』(赤々舎)など。作家活動の他に、『コレクション 戦争×文学』(集英社)、『石原慎太郎の文学』(文藝春秋)をはじめ書籍の題字なども多く手掛ける。
作品収蔵先:高橋コレクション(東京)、ヴァンジ彫刻庭園美術館(静岡)、うつわ菜の花(神奈川)など。
https://kasetsuws.exblog.jp/
撮影:志鎌康平
1974年茨城県生まれ。人々の日常、人間と自然環境の移動などをテーマにフィールドワークを行い、写真やテキストなどによる作品を発表する。主な展示に、中房総国際芸術祭「いちはらアート×ミックス2014」、「KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭」、2018年 個展「The Second Stage at GG」#46「ここがどこだか、知っている。」(ガーディアン・ガーデン)など。写真集に、詩人・谷川俊太郎とコラボレーションした『生きる』(ナナロク社)などがある。
1971年茨城県生まれ。イメージフォーラムのフェスティバルディレクター(2001-10)を経て現在はフリーランスのキュレーター。あいちトリエンナーレ(2013)、東京都庭園美術館(2015,16)、青森県立美術館(2017,18)などでキュレーション。

茨城県では、アートを活用した地域主体のまちづくりのための事業に取り組んでいます。《メゾン・ケンポク》はその一環として、2018年12月にオープンしました。丘の上に立つ、かつて大きな料亭だった建物を活用し、長期滞在できるレジデンスと、イベントや制作活動を行うことができる設備を順次、整備中です。3階には風情のある56畳の大広間と舞台があり、窓からは常陸太田市の美しい町並みと山々を見渡すことができます。アーティストで茨城県北地域おこし協力隊の日坂奈央(ファッション・デザイン)と松本美枝子(写真家)が常駐し、ここを拠点にさまざまなアート・プロジェクトを発信していきます。
facebook @maisonkenpoku | twitter @maison_kenpoku | instagram @maison_kenpoku
茨城県常陸太田市西一町2326
Tel:080-8740-6912
JR水郡線常陸太田駅より徒歩15分/常磐自動車道日立南太田ICより車で15分
駐車場は常陸太田市郷土資料館向かいの市営駐車場をご利用ください(無料)
写真家ユージン・スミスが1960年代に日立を撮影していたことを知ったのは、昨秋のこと。さらに調べると、日立市郷土博物館の学芸員、大森潤也さんが、20年以上もその研究を続けていることが分かったのだった。
そして調べれば調べるほど、これほどの写真家が撮影した痕跡や成果が地元・日立にほとんど残ってないということも分かっていった。それはなぜか?
地域で生まれた重要な資料や作品が都市部へと流出し、地域には残りにくい、ということ。そして地域ではそういった資料や作品、情報がほとんど伝わらず、価値づけられにくい、ということ。これは実は博物学、そして美術における大きな問題なのだ。
大森さんの素晴らしい研究を地域に改めて紹介しながら、この問題を地域でシェアできないだろうか? それが今回の私の「茨城県北サーチ」だった。大森さんの研究は、私に新たな課題を示してくれたのだ。
そして華雪さんのプログラムにも同じことが言えるだろう。江戸時代から続く西ノ内紙を愛する人たちの熱意を、真摯に受けとめたアーティストによる、新たな展開がはじまるのかもしれない。
さてこの「茨城県北サーチ」を、福島県から二年続けて熱心に参加してくれている方から会の終わり際、こんな言葉をいただいた。
「このプログラムがすごくいいからこそ、こういう活動をゆっくりとやってほしい。」
こんな言葉こそが、私たち文化に関わる人間の糧だ。
今回のリサーチを通して私は、重要な文化を地域内外で等しく価値があるものとして捉え直すシステムを作りたい、と改めて思うようになった。慌てずに、でも決して消えることのない、持続可能な文化の発信とその仕組みを作っていきたい。
松本美枝子
この文章を書いている2020年3月現在、コロナウイルスの封じ込めは実現していない。経済にも文化にもさまざまな影響を及ぼしているが、世界中の人びとが一斉スタートで情報を得、対策を練るさまをリアルに生きているともいえる。情報は根拠がはっきりして整理されたものばかりではなく、デマにより健康リスクを高めるケースも生じた。
今年度は防疫対策徹底の上、二人のゲストに二つの場所を拓いてもらった。個人的には、「作品」という制度や概念の外側に光を当てた機会に感じた。初日は日立市郷土博物館の大森潤也さんに1960年代に作られた地元企業・日立製作所の海外向けのPR誌の存在を紹介していただいた。撮影者はなんとユージン・スミス! 写真家はクロッピングや焼き込みなど、後加工の名手でもあったことを知る。だからこそ、助手で参加していた西山雅都、天野行造、森永純さんらによる本誌不採用のカットが、アウトオブフレームである故に、地域の活きた情報として文化遺産になりえるかもという考察に二度驚いた。
二日目は常陸大宮市の紙のさと 西ノ内和紙資料館で華雪さんによる漢字「藝(芸)」にまつわるディスカッションと“すき絵”体験。書家が古代文字の成り立ちを紹介、筆で書いて(描いて)みながらその軌跡の実感について印象を分かち合った。元来、漢字には書き順もなく、美的な基準もなかったそうだ。つまり上手いや正しいという作品評価はなかった! それをふまえ、ほとんどの方が未体験の”すき絵”技法で藝の字に挑む。植物とそれを植える人に分解された表象を、和紙という植物素材に植えていく偶然の入れ子構造。万人が用いる文字という道具に私的な時間が生まれた。
澤隆志